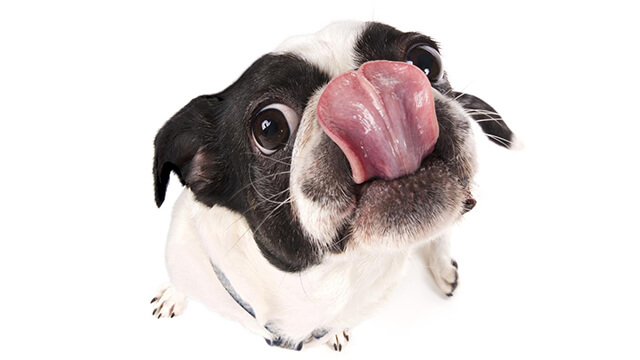
ロイヤルカナンは、消化吸収が良い原料を使っている「スキンケアプラス」を食べさせることで食ふんを防止できるとされています。(参考ロイヤルカナン スキンケアプラス)
ですが、食ふんをする理由によっては、フードを変えるだけでは食ふんを止めさせることができない場合もあります。
この記事では、ロイヤルカナンで食ふんが防止できる場合と出来ない時の対処法を紹介しています。
うんちの臭いがキツイ子はロイヤルカナンで食ふんを止めさせられるかも

食べているドッグフードの消化が悪い時には、うんちに中にドッグフードの風味が残り食ふんをする原因となります。
消化器官が未発達な子犬の時期に食ふんが多いのも、うんちにドッグフードの風味が残っているためとされています。
スキンケアプラスは、皮膚トラブル用のドッグフードですが、超高消化性小麦タンパクを90%以上使用しており「消化率が高く、便のにおいが少ない」という特徴があります。
上記の特徴から、食ふん対策として獣医師などから推奨されることが多いドッグフードです。
ですが、消化吸収の良いロイヤルカナンへとドッグフードを変えても食ふんが改善されない場合もあります。
そんな時には、今食べてるドッグフードにふりかけて食べさせる「食ふん防止サプリプロキュア」を試してみてください。
このサプリは乳酸菌や酵素を摂取でき、食ふん防止だけでなく「毛艶が良くない・皮膚がカサカサしている」ワンコにも効果的です。
詳しくは公式サイトで確認してみてください→プロキュア公式サイトを見てみる
ドッグフードを変えても、食ふんを防止できない場合
ドッグフードを変えても食ふんが改善されない4つの原因として
この4点の原因が考えられます。
それぞれについての対策を紹介していきます。
食事量が少なく空腹感を満たすために食ふんをしている時の対策
ワンコの食事の様子を観察し、1日の食事量が足りているのかを確認します。
子犬の場合は1食の食べる量に限りがあるので、1日に3〜4食に小分けに食べさせてみてください。
ワンコが見せる空腹のサインは
- 食べ終わった後に吠える
- 食べた後もご飯のお皿の前から動かない
- 前足で催促する
食後や普段からワンコの様子を観察して、食事量の調整をしてください。
うんちの臭いを消して自分の痕跡を消す行為として食ふんをしている時の対策
食ふんをしてしまうワンコの行動は
- 敵から身を守る
- 巣をきれいにする
といった、犬に元々備わっている本能的な行動です。
ですので、食ふんをさせないようにするには、うんちをしたらすぐに片づけるのが効果的です。
また、留守番中にゲージ内で食ふんをする場合には、寝る場所とトイレの位置を離すなど飼育環境を見直すことで食ふんを防ぐことができます。
成犬であれば、規則正しい生活リズムを作ることで、決まった時間に決まった場所で排泄するトレーニングも可能です。
飼い主の興味を引くために食ふんをしている時の対策
うんちやトイレトレーニング中の失敗に、飼い主が過剰に反応してしまうと、ワンコにとっては「飼い主が興味を持ってくれた」と勘違いすることがあります。
ですので、失敗しても慌てず怒ったりせずに後始末をすることが大切です。
食ふんをしているところを見つけた時も、声をあげての注意ではなく一言「ダメ」とだけ言って止めさせるほうが、食ふん防止に効果があります。
子犬の時期には、大声で注意したくなりますが、「ダメ」をしっかりと伝えることで、行為の良し悪しを理解できるようになります。
ストレスや不安感から食ふんしている時の対策
ストレスや不安感から食ふんをしている場合には、食ふんをしても叱らないようにワンコと接することが大事です。
また、たくさん遊んであげたり散歩時間を増やすなど、愛犬とのスキンシップを多くとることで食ふんが改善される場合もあります。
ワンコを不安にさせないよう、これまで以上に愛情をもって接するように心がけてみてください。
食ふんをすることでの健康被害

ワンコや飼い主にとってのリスクは2つ
- 食ふんするのが自分のウンチだけでなく他の犬のウンチも食べてしまう
- 犬の体内に寄生虫や病原菌がいた場合は、飼い主に病気が感染する
など、ワンコの口が臭う・不衛生といった精神的なデメリットのみならず、健康を害する場合もあります。
食ふんがワンコに与えるリスク
自分がしたウンチを食べてもあまり影響はありませんが、他のワンコのウンチを食べてしまう「食ふん症」になると寄生虫や細菌・ウィルスの感染リスクが大きくなります。
食ふんしたワンコが飼い主に与えるリスク
食ふんをしたワンコに顔を舐められた場合には、犬回虫などの寄生虫が人へと感染する場合もあります。
特に小さなお子様のいる家庭では、動物由来感染症のリスクが高いので注意が必要となります。
口の周りや傷口をなめられてうつる場合もあります。動物の咳やくしゃみを直接受けたりすることで感染する病気もあります。動物の体についている病原体も直接伝播の原因となります。特に子どもでは動物に触って糞などで汚染した手を口に持って行くことで感染するルートもあると考えられています。
厚生労働省:動物由来感染症についてから引用
犬が食糞するのをやめさせるにはどうしたらいいですか?
犬が食糞をすることは飼い主にとって驚きや不快感を与える行動ですが、これは比較的一般的な行動です。食糞の原因にはさまざまなものが考えられますが、主に以下のような理由が挙げられます。
- 栄養不足: 食糞は、犬が必要な栄養素を満たしていない場合に見られることがあります。犬が体内で不足している成分を便から再摂取しようとするためです。この場合、栄養バランスの良いフードに変更することが効果的です。
- ストレスや不安: 飼い主がいなくなるときや新しい環境に変わったときに、犬がストレスを感じ、そのストレスを解消するために食糞をすることがあります。環境の安定化と、犬がリラックスできる空間を作ることが重要です。
- 好奇心: 特に子犬は、好奇心から食糞をすることがあります。トイレの後に便を片付けるタイミングを見逃さないようにし、犬がトイレ後にすぐに遊んだり、他の注意を引けるようにしましょう。
食糞をやめさせるためには、犬が食糞をしないように環境を管理し、トイレ後に即座に片付けることが大切です。また、犬の栄養状態を見直し、ストレスを減らすための行動訓練を行うことも効果的です。
犬がウンチを食べる癖は治りますか?
犬がウンチを食べる癖(食糞)は、十分な対策を講じることで治る可能性が高いですが、すぐに治るわけではありません。まずは食糞の原因を特定することが治療の第一歩です。食糞は栄養不足やストレス、不安感が原因であることが多いため、それを解消するためのアプローチを行うことが求められます。
もし栄養不足が原因であれば、バランスの取れた食事を与えることで食糞をやめさせることができます。適切な栄養素を与えることで、犬が便から栄養を再摂取する必要がなくなります。また、ストレスや不安が原因の場合は、環境を安定させるための工夫が必要です。例えば、毎日の散歩や遊び、精神的に刺激を与えるおもちゃなどで、犬の不安を和らげることができます。
食糞の癖は、飼い主が忍耐強く対応することで治ることが多いです。日々のケアと訓練、環境調整を行い、犬にとって心地よい生活を提供してあげることが大切です。
犬 食糞 何歳まで?
食糞は主に若い犬に見られる行動であり、特に子犬や成長期の犬に多く見られます。多くの場合、犬が生後6ヶ月から1歳ごろまでに食糞の習慣を示すことがありますが、年齢とともに治ることもあります。しかし、食糞が続く場合には原因を調べる必要があります。
子犬は好奇心が強いため、食糞をすることがありますが、大人の犬になると、一般的にこの行動は減少します。もし成犬になっても食糞が続く場合は、栄養不足、ストレス、または他の健康問題が原因である可能性があるため、獣医師に相談することをお勧めします。
適切な対策と訓練を行うことで、多くの犬は食糞の習慣をやめることができます。年齢を重ねるにつれて、この行動は自然に改善されることが多いですが、しっかりとした管理が必要です。
まとめ
食ふんはあまり気にせず放っておけば良いよ、という意見もありますが、やはり臭いや健康被害のことを考えると、できるだけ早く食ふんは止めさせたい行為です。
フードを変えたり、生活環境の見直しなどで改善する場合もありますが、なかなかうまくいかない場合には、食ふん防止のサプリを活用するのも効果的です。
今食べているフードを変えることなく、食ふんを防止でき腸内環境を整え健康的な体づくりをサポートしてくれます。
まず便を早く片付け、そもそも食べる便が近くにない状態にすることが大切です。
時間とともに解決することもありますので、食ふんをしても叱らず、騒ぎ立てずに見守っていきましょう。
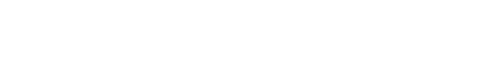
コメント